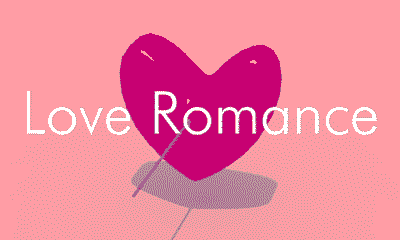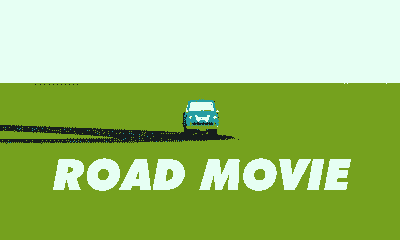ワイルド・レンジ
一目逢ったその日から恋の花咲くこともある…を地で行くが、何とももどかしい展開だ。でもアネット・ベニング演じるところのスーさんがいいですね。
いまさら言うのもナンですが、西部劇は時代劇に相当するけど、圧倒的に作り易いんじゃないかと思います。マゲは要らないし、家並みも作り易いもんなあと改めて感じる次第です。
さて内容だが、概ねイイ感じで感情移入しやすい。
いぶし銀のロバート・デュバル演じるところのボスを立てるケヴィン・コスナーには実は暗い過去があるが、ボスに拾ってもらったお陰でなんとか人間らしくなれたという恩義がある。
あるトラブルが原因でドクターの奥さんと思しきスーに出会う。これが現代劇だと、即、不倫ものに発展しそうだが、そこは西部劇、まだまだ善玉は礼節をわきまえている表現が心地よい。
最初のうちはエラくノンビリとした牧歌的なシークエンスの連続で、たっぷりとカウボーイの生活を堪能させてくれる。中盤以降になるとガンファイト中心になってくるが、ヒーローヒーローしたスーパーマン的なそれではなく、どこか人間味のある、言い換えればリアリティのあるガンファイトが展開するのは好感が持てる。勝てたのはあくまでも運が良かった的な扱いだ。
どうせ死ぬんだからと、最高級のチョコと葉巻を買う
と、良いこと尽くめだと言いたいのだが、チト腑に落ちない点もある。
●ラスボスに引導を渡そうかどうしようかと迷うシーンがあるが、この時、画面手前で意味深に人が映る。これがヘンに意味ありげなのに結局何も起らないので、肩すかしを喰ってしまう。
●主人公が隠すように口を拭うシーンがあるのだが、これが時代劇ならほぼ間違いなく労咳(結核)を暗喩しているが、結局何も起らない。伏線を張るだけ張って回収していないような気になってしまう。このシーンは要らないんじゃないのかな?
●主人公の愛の告白が何ともモッチャリし過ぎている。たそがれ清兵衛でも、もっとハッキリ申し上げているぞ。わざわざ酒場に呼び出しておいてアレはないやろ。よっぼどスーさんのほうが男らしい。
●そしてそこからの時間軸がどうもよく判らないのが、カタルシスを妨害しているとしか言いようが無い。一旦どこか遠くへ行って何ヶ月か経ったように見えるんだが、そうでもないようにも見える。あの展開はわざとなのか?感動を薄めよう薄めようとしているのではないか?もっとこう嘘でもいいから「鍵泥棒のメソッド」的な終り方を期待していたんだがねえ。そこが最大の難点ですな。
»»鑑賞日»»2019/01/05